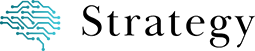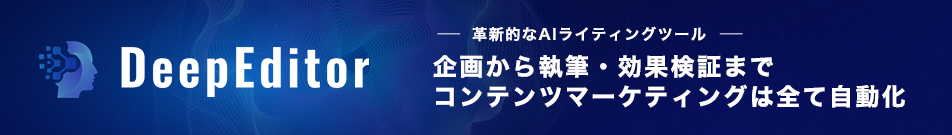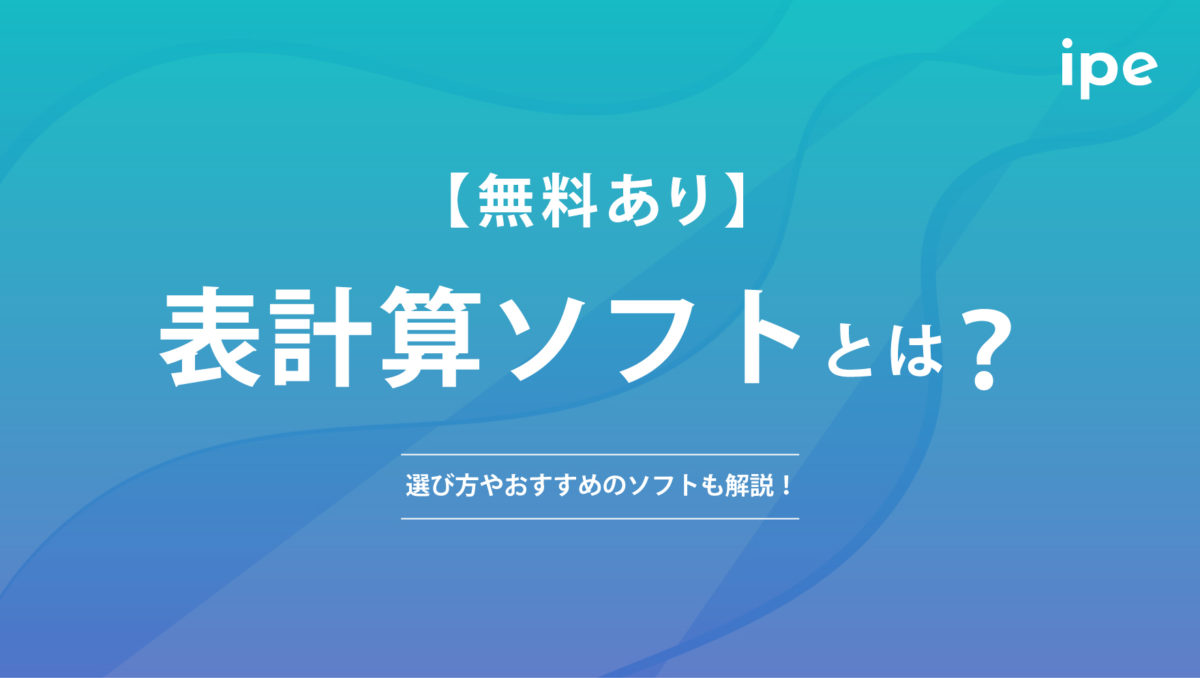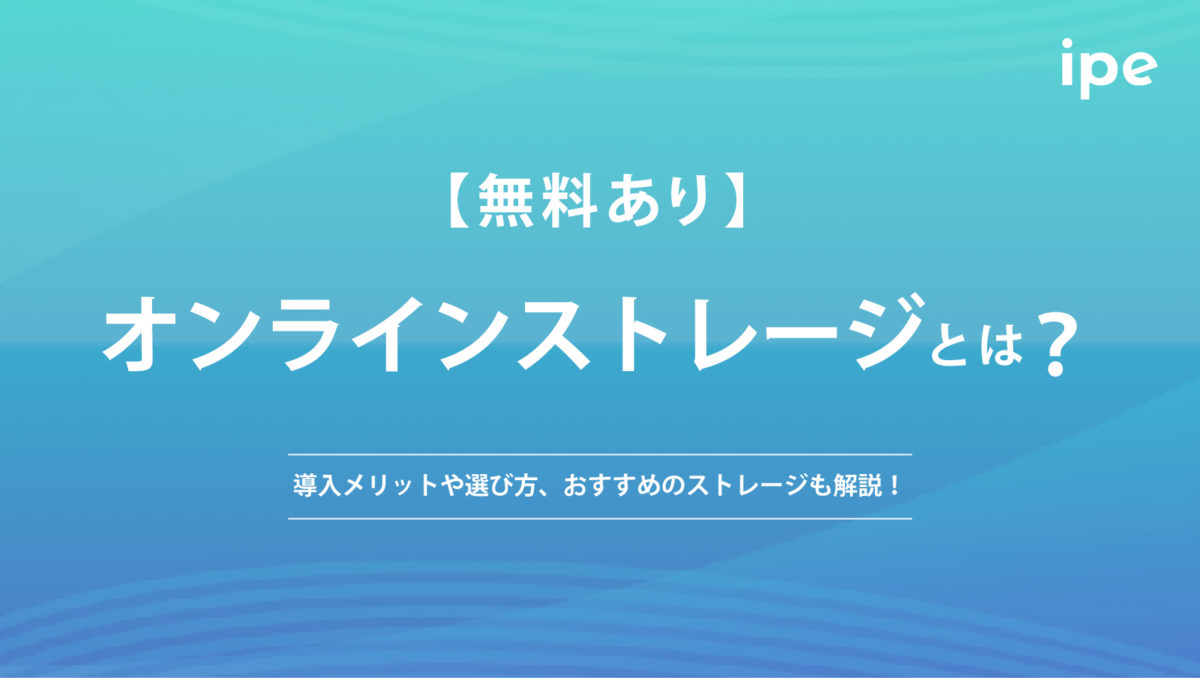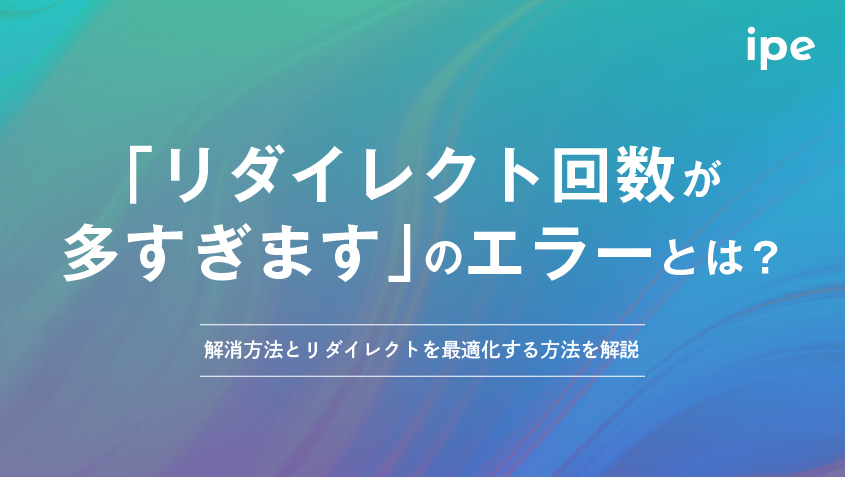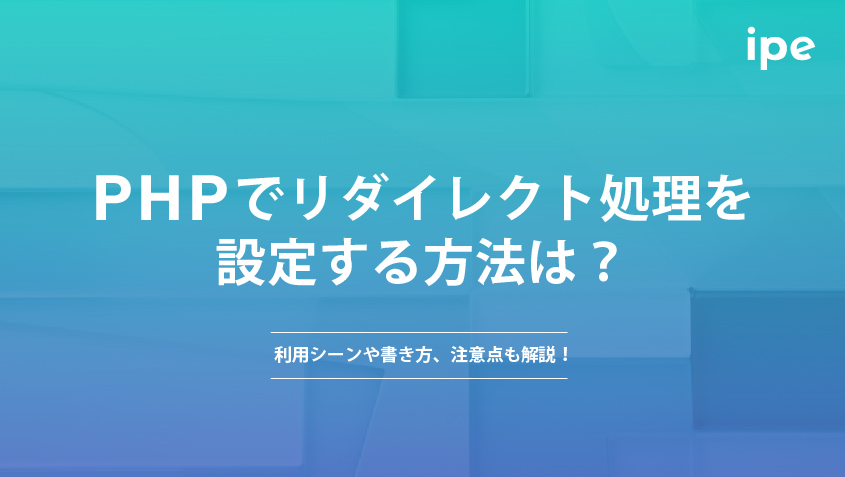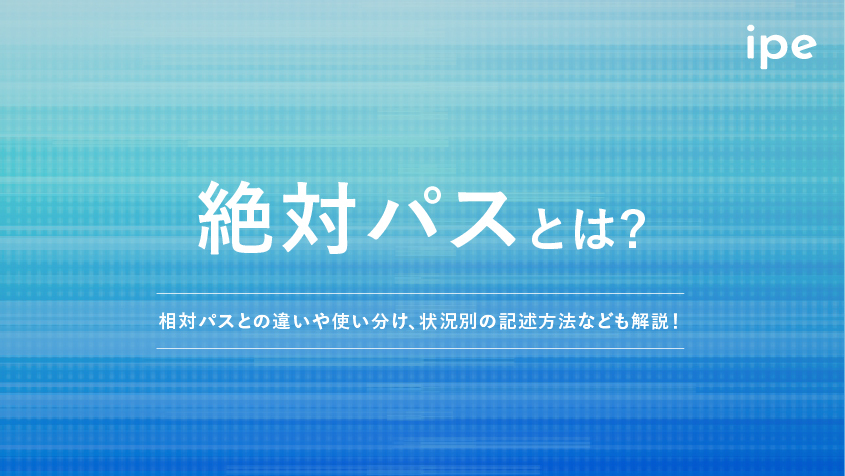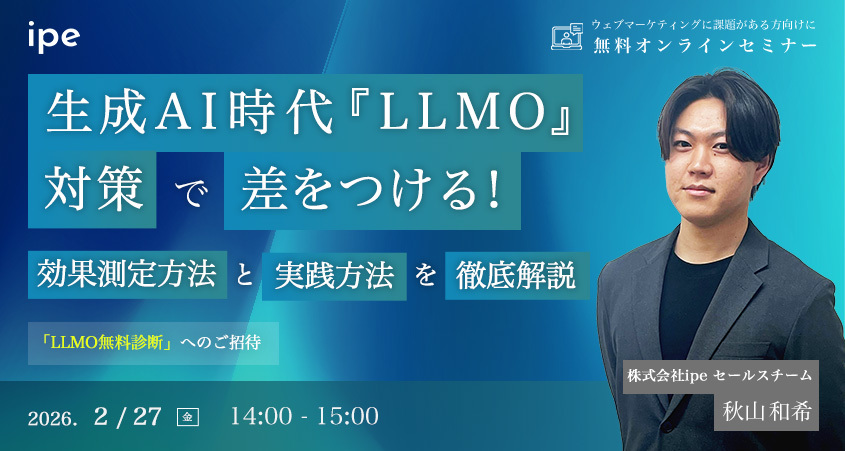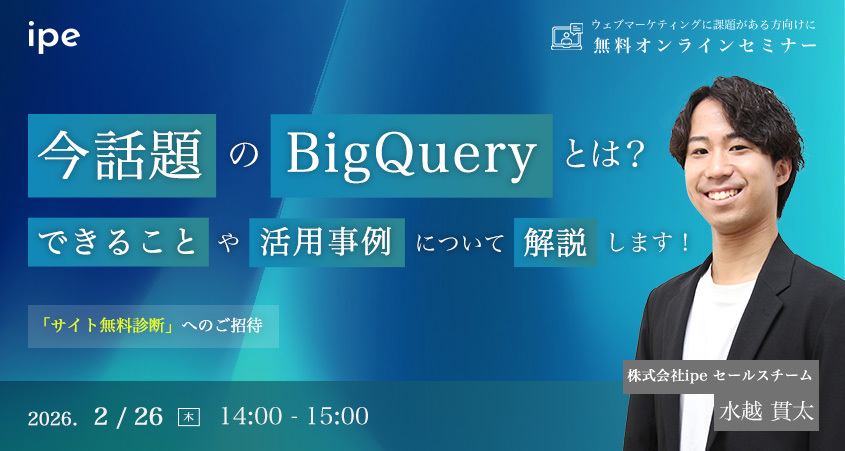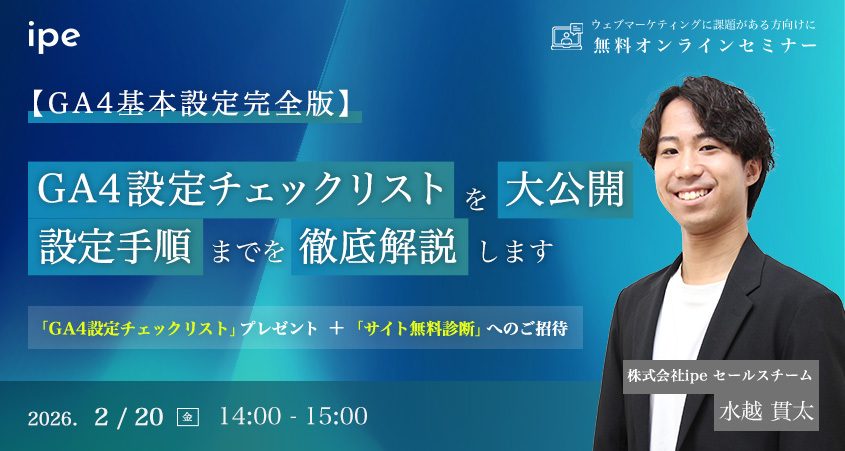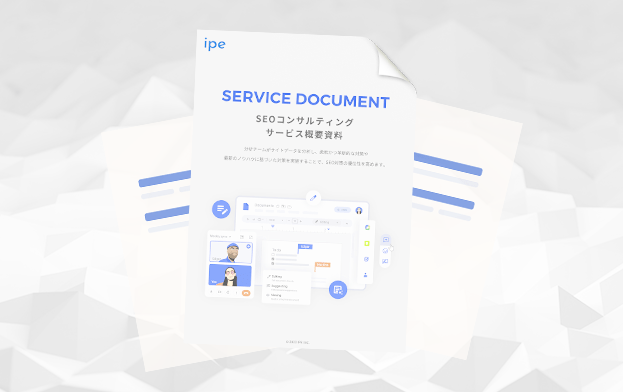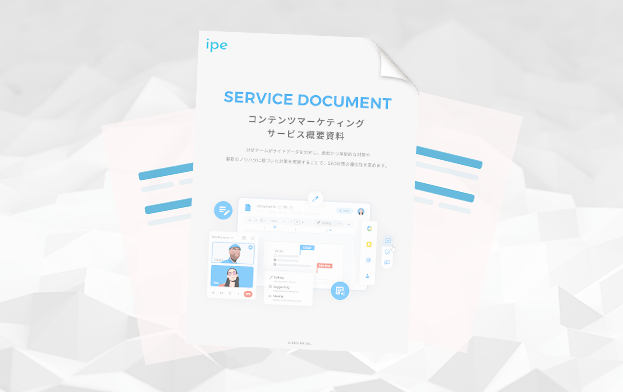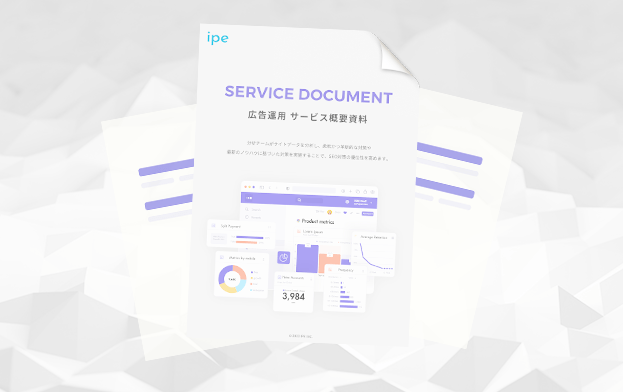【2023年最新】SEOチェックリスト18項目!内部対策の重要性とその効果を解説
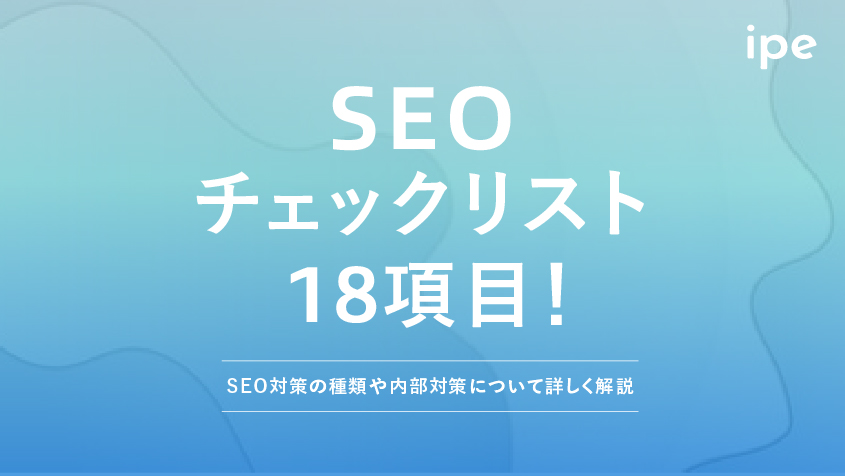
企業が自社サイトにSEO対策を実施するとき、最低でも18項目はチェックしたほうがよいでしょう。この18項目はプロのSEO会社が顧客企業のサイトに対して行っているもので高い効果が期待できます。検索上位表示を狙うための「最初の18ステップ」を紹介します。
SEO対策の3つの種類
SEO対策には大きく分けて下記の3種類があります。
|
コンテンツSEO
コンテンツSEOは自社サイトのコンテンツを充実させる手法です。良質なコンテンツや価値ある情報を掲載していると、検索エンジンは「これは閲覧者の役に立つサイトである」と認識して検索順位の上位に持っていこうとします。そのためコンテンツ対策がSEO対策になるのです。
外部対策
外部対策は自社サイトのリンクを他のサイトに貼る手法です。被リンクが増えることで検索エンジンは「必要とされているサイト」と認識し、やはり検索順位を上げます。また企業がSNSを使って自社サイトの拡散を図れば、それも被リンクを増やすことと似た効果が得られるので、これも外部対策に数えられます。
内部対策
最後に内部対策ですが、これはサイトの内部構造を改善し最適化する方法です。内部構造を適切にすると検索エンジンが「しっかりしたサイト」と認識し、上位表示がかないます。
あとで紹介する18項目は原則、内部対策に属します。
内部対策は近年重要性が増しているので、さらに詳しく解説していきます。
内部対策が近年重視されている理由
SEO対策の中でも、とくに内部対策が重要視されているのは、作業が定型化されていて、なおかつ効果がわかりやすい形で出るからです。すなわち、内部対策は「やることが決まっていて」、「やればやっただけ効果が出る」といえます。
内部対策と比べ、外部対策は他社の要素が絡むので、自社だけではどうしようもない部分が出てくるのです。また、コンテンツSEOに関しては、よいコンテンツをつくっても内部構造が不適切だと検索エンジンの評価が上がりにくい傾向にあります。
もちろん、外部対策やコンテンツSEOも成功すれば高い効果を発揮するのですが、早く効果を得られる内部対策を先に試すのがおすすめです。
まず検索エンジンの仕組みを理解しよう
内部対策を成功させるには、検索エンジンの動きを理解するのが重要です。検索エンジンの動きは、クロールとインデックスという二つの重要なプロセスによって成り立っています。
クローラーとは、検索エンジンのロボットです。クローラーは検索結果を出す前に、インターネット上のウェブサイトを巡回し、情報を収集します。
クロール後に行われるのは、インデックスと呼ばれるプロセスです。インデックスでは、クローラーが収集した情報は検索エンジンのデータベースに登録されます。インデックスされた情報は、検索クエリに対する結果の順位付けのために使用されるものです。
したがって、クローラーの効果的な巡回とインデックスの精度が、検索結果の品質と順位に直接影響を与えます。以下は、クロールとインデックスのときに作用しやすい内部対策チェックリストです。
SEOチェックリスト18項目
以下は18項目のSEO対策チェックリストです。この順に解説していきます。
| SEOチェックリスト |
|---|
|
クローラーに作用するSEO対策のチェックリスト
クローラーは世界中のサイトを巡回して情報を集めるロボットです。這いまわるという意味のcrawlが語源です。クローラーが集める情報は、HTMLやテキストファイル、画像、PDFなどです。
クローラーに作用するSEO対策は以下のとおり。
|
1つずつ解説します。
XMLサイトマップを作る
XMLサイトマップは、サイト内の全ページをリスト形式で表記したものです。
サイトにXMLサイトマップがあると、閲覧者はどこに自分が求めるコンテンツがあるのかが一目でわかります。そのためXMLサイトマップがあるサイトは検索エンジンに評価されます。
内部リンクを最適化する
内部リンクとは、サイト内の複数のページどうしをつなぐ手法です。
例えばAというページでaについて解説していて、そのなかでbについて触れたとします。そして同じサイトのなかに別にBというページがあり、そこでbについてさらに詳しく解説していたら、ページAにページBのリンクを貼っておくと、閲覧者は簡単に遷移してbについて知ることができます。
これも閲覧者の利便性を高めているので、検索エンジンは評価します。
構造化データをマークアップする
構造化データとは、検索エンジンにHTMLで書かれた文字情報を認識させるためのデータのことです。そして「構造化データをマークアップする」とは、構造化データをHTMLのタグを使って実装することをさします。
検索エンジンはコンテンツに書かれてある「言葉そのもの」は理解できないので、検索エンジンに正しく認識させるには構造化データが必要になります。
パンくずリストを設置する
ユニークな名称ですが、これはグリム童話の「ヘンゼルとグレーテル」に、森のなかで道に迷わないように歩きながらパンくずを残していったというシーンがあり、それになぞらえています。
パンくずリストは、サイト内の複数のページの階層構造を示したものです。例えば以下のような表記になります。
衣食住>食>主食>パン>クロワッサン
サイト内のあるページでクロワッサンさんについて解説したとします。このページは、パン・グループに属し、パン・グループは主食グループに属し、主食グループは食のグループに属しているとします。そして食のグループは衣食住グループに属しています。
クロワッサンのページに「衣食住>食>主食>パン>クロワッサン」と記載されていれば、ページの階層構造が一目で理解できます。
この階層構造の表記を、パンくずリストといいます。
サイト内にパンくずリストが表示されていると、閲覧者は次に訪問したいページをすぐにみつけることができます。
SSLを適用する
Secure Socket Layer(SSL)は、インターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組みです。
SSLを適用することで、そのサイトの安全性が高くなるので検索エンジンの評価が高くなるのは当然です。なおSSL化したサイトのURLはhttpsとなります。
URLの構成を見直す
「URLの構成」という概念は少し難しいので例えを使って説明します。
1つのサイトを1丁目とすると、そのサイトのなかの複数のページは、1丁目のなかにある1軒1軒の家になります。そして1軒1軒の家にはそれぞれ異なる住所が割り振られていて、それが各ページに割り振られたURLになります。
住所は1軒1軒異なりますが、同じ町内のなかだと似通ってきます。例えば「東京都○区△町1」の隣が「東京都○区△町2」となるようにです。
1つのサイト内の各ページのURLもこれと同じように、1つひとつ異なるのですが似たURLになります。
URLは1)スキーム、2)サブドメイン、3)トップレベルドメイン、4)セカンドレベルドメイン、5)サブディレクトリの5つの要素で構成されています。これが「URLの構成」です。
サイト内のページのURLの構成を見直したり正規化したりすることで「URLの構成が整理されたしっかりしたサイト」になり、検索エンジンの評価が高まります。
クロールエラーを解消する
検索結果の順位づけは、検索エンジンのクローラーがサイトの情報を収集することから始まります。そうであれば、クローラーがそのサイトをきちんと調べることができなかったら、どれだけよいコンテンツをサイトに掲載しても上位表示はかなわないことになります。
これをクロールエラーといいます。
したがってサイトの管理者は「クローラーに正確に巡回してもらえるよう」にする必要があります。これがクロールエラーを解消する作業です。
クロールエラーはリンク切れやステータスエラーなどによって生じるので、実際の作業はそのような不具合をなくしていくことになります。
インデックスに作用するSEO対策のチェックリスト
クローラーが集めたサイトの情報は、検索エンジン運営会社のデータベースに登録されます。このとき登録される情報は、それがどのようなコンテンツなのか、そこに添付されている画像ファイルはどのような内容なのか、といったようにかなり具体的なものです。
データベースに登録されることを「インデックスされる」といいます。
インデックスに作用するSEO対策には次の5項目があります。
|
1つずつみていきましょう。
タイトルとディスクリプションを適切に書く
この場合のタイトルとは、文章コンテンツ、つまりサイト内の記事のタイトルのことです。ディスクリプションは要約のことです。
記事はいきなり本文を書き始めるのではなく、その冒頭にタイトルとディスクリプションを書くようにしましょう。タイトルとディスクリプションが書いてあると、閲覧者はすぐにどのような記事なのかがわかり、必要な情報か不要な情報か判断できます。これは閲覧者に有益なので、検索エンジンが評価します。
見出しの書き方を整える
タイトルが記事全体の概要を記したものとすると、見出しは各段落の概要を記したものです。見出しも閲覧者が記事を理解するのに役立ちます。
理想は、タイトルとディスクリプションと見出しをチェックするだけで、その記事に大体どのような内容が書いてあるか推測できるようにすることです。
それで検索エンジンは見出しもチェックするわけです。
画像を正しく使う
文字だけの記事と、写真やイラストが挿入されている記事では、後者のほうが読み進めやすく、理解も進むと思います。
そのため検索エンジンは、記事のなかの画像が適切かどうかも判定します。
画像の選定もSEOに影響することを覚えておいてください。
適切にリンクを貼る
サイト内のリンクは閲覧者の情報収集に役立ちます。そのため適切なリンクをサイト内や記事のなかに貼りつけることはSEO対策になります。
リンク切れの有無を確認する
リンク切れは、ユーザー体験を損ない、サイトの信頼性にも影響を与えます。検索エンジンは、リンク切れが多いサイトをメンテナンス不足と判断することがあり、これがSEO評価の低下につながることも。
そのため、ブログやウェブサイトを運営する際には、定期的にリンク切れがないかをチェックし、必要に応じて修正することが重要です。これにより、サイトの品質を保ち、訪問者に良好な体験を提供することができます。
インデックス登録エラーを解消する
インデックスでは登録エラーが発生することがあり対策が必要です。このSEO対策は総合策のような位置づけになります。
インデックスの登録エラーはさまざまな要因によって発生します。新規ドメインのため、ペナルティを受けているため、URLの正規化がなされていないため、などです。
登録エラーが発生したら、原因を1つずつ潰していく必要があります。
ユーザビリティ向上によるSEO対策のチェックリスト
ユーザビリティの向上とは、閲覧者が閲覧しやすいサイトをつくること、と言い換えることができるでしょう。これもSEO対策になります。
そのための施策には次の6項目があります。
|
文字サイズを適切にする
「文字サイズまで検索エンジンはチェックするのか」と感じるかもしれませんが、チェックします。なぜなら文字サイズは情報量と読みやすさの両方に関わるからです。
大きな文字は強調されるので閲覧者の印象に残りやすいのですが、パソコンもスマホも画面の広さが限られているので文字が大きくなると情報量が減ります。
そのため最適な文字を選択する必要があります。
「404エラーページ」を設定する
あるサイトにアクセスしたものの、そのサイトが存在しないとき「404」と表示されます。404はエラーメッセージの1つです。
例えば、自社サイトに人気の記事があり、その記事が載っているページのおかげでアクセス数を稼ぐことができていたとします。ところがその記事の内容が古くなったので、別にページに新しい内容の記事を載せたとします。
このとき、元のページを削除してしまうと、閲覧者がそのURLにアクセスしたときに404が出てしまいます。404が出てもSEOに悪影響は及ぼさないとされていますが、しかしその情報を求めていた閲覧者は落胆します。アクセス数も減ってしまうでしょう。
しかし情報が古くなってしまった記事が載っている元のページをいつまでも存続させてしまうと、閲覧者に不正確な情報を伝えることになり、これは正しくないことです。
そこで404ページができてしまったら301リダイレクトという設定をします。
301リダイレクトは転送処理です。これを施せば、閲覧者は新しいページに飛ぶことができます。閲覧者に親切であるだけでなく、これまでのアクセス数を維持できる効果が期待できます。
ページ表示速度を高速化する
いわゆる「重いサイト」は閲覧者に閲覧疲れを起こします。そしてあまりにページの表示が遅いと離脱につながってしまうでしょう。
したがってページの表示速度が速いサイトほど、閲覧者に親切であるといえます。
ページの表示速度が遅くなる原因には、画像圧縮をしていない、コンテンツが重い、プログラムを多用している、ことなどがあります。これらを解消することでページ表示スピードが速くなります。
モバイルファーストインデックスに対応する
特にグーグルは、モバイルファーストを強調しています。この場合のモバイルとは主にスマホのことです。
つまり、パソコンでサイトをみる人より、スマホでサイトをみる人が増えてきたので、検索エンジン運営会社は、モバイル(≒スマホ)での閲覧に適合したサイトを評価するようになったのです。この考え方を具現化したのがモバイルファーストインデックスです。
モバイルファーストインデックスに対応するために、スマホで閲覧しやすいサイトをつくっていきましょう。
広告の表示を適正にする
リスティング広告とは、閲覧者が検索エンジンでキーワード検索をしたときに、そのキーワードに関連した広告が表示される仕組みです。
したがって、検索エンジンにキーワードを入力して上位表示を目指すSEO対策と似ている部分があります。
しかしグーグルは、リスティング広告を多く出している企業のサイトを、SEO評価で優遇することはない、という方針を持っているとされています。
もしリスティング広告を多く出しているという理由でその企業のサイトのSEO評価を高くしてしまうと、SEO評価をお金で買うことになってしまい、グーグル検索の信頼が揺らいでしまうからです。
では、リスティング広告を出すとSEO的に不利になるのかというともちろんそのようなことはありません。
広告の表示を適正にすることで、広告効果を高めながら、SEOに悪影響を与えないようにすることができます。
そしてリスティング広告とは別にSEO対策を講じることで、SEO評価を獲得することができます。
インタースティシャルの利用を限定する
インタースティシャルはWeb広告の一種で、サイトのページ切り替えや遷移のときに画面に表示される広告のことです。
インタースティシャル広告には、閲覧者の閲覧を邪魔するマイナス効果が生まれます。そのため検索エンジンは「しつこい」インタースティシャル広告をマイナス評価します。
ただ、インタースティシャル広告は訴求力が高いので魅力的な手法です。また「しつこくない」インタースティシャル広告はSEO上のマイナス効果を生まない可能性があります。
したがって節度ある使い方をすれば、インタースティシャルの広告効果とSEOを両立させることができます。
チェックすべき内容は頻繁に変わっていく
SEOの世界は絶えず進化しており、チェックすべき内容も常に変化しています。最近ではAIの進化により、AIを活用したSEO戦略の重要性が増しているのもその一例です。
また、ユーザーの多様化する検索ニーズに合わせ、画像や音声、動画検索などにも対応する必要があります。SEO対策は一度行ったら終わりではなく、定期的なアップデートと適応が求められます。効果的なSEOを維持するためには、定期的な評価と適応が必要であり、適切なチェックリストとツールの使用がその実現に不可欠です。
なお株式会社ipeでは、全69項目のSEO攻略チェックリストツールを公開しています。300社のコンサルティングノウハウを基に作成された、確かなノウハウです。
18項目を遥かに上回る、幅広いSEO対策に関する内容が含まれています。この機会にチェックリストをご覧になってはいかがでしょうか。
18項目のチェックを終えたら次に進みましょう
この記事で紹介した18項目はSEO対策の「最初の18歩」になるので、確実に1歩1歩進めていってください。
しかしSEO対策はこれだけでは終わりません。内部対策にはまだほかの施策がありますし、内部対策の効果が出てきたら、引き続き外部対策やコンテンツSEOに取り組みたいところ。
SEO対策で疑問が湧いたら、ぜひipeのSEO無料相談を利用ください。
SEOに関するご相談があれば、ぜひipe(アイプ)へご相談ください。